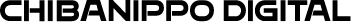デジタル化の罠
「83.4%」。この数字、何の数字かわかりますか? 実は日本人全体でインターネットを使っている割合です(2020年、総務省)。年齢別にみても、10~50代で9割超、60代で8割超、70代で約6割がネットを使っています。
ネット利用が増えつつある背景もあって、2021年9月にデジタル庁が設立されるなど、国を挙げての「デジタル化」「IT化」「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」といったデジタルを活用した取り組みがさまざまな場面で進んでいます。
ですが、現状、事業者や組合の皆さんはどこまで、この「デジタル化」に取り組めているでしょうか? 日本人の8割超が当たり前のようにインターネットを使いこなす時代にもかかわらず、なかなか事業そのものや事業の周知・広報PRにネットをはじめとするデジタル技術を活用できていない先は多いのではないでしょうか?

本稿でご紹介する臼井地区商店会連合会は、数年前から「デジタル化」をキーワードに研究会を続けてきました。毎月研究会を実施する意欲的な姿勢からさまざまな成果が生まれてきましたが、一方で「デジタル化の罠」とでもいえる事態にも直面していました。
その「罠」とは、簡単にいえば「デジタルを活用することが目的になってしまっている」状態です。「デジタル化の罠」にはまってしまうと、本質的に取り組まなければならない課題解決を忘れてしまいがちです。
本稿では、臼井地区商店会連合会が2021年度の研究会を通して、どうやって「デジタル化の罠」から一歩抜けだし、新しい視点でデジタル化と向き合い始めたかをご紹介したいと思います。
新たな展開:コミュニティスペースをつくる
臼井地区商店会連合会は、佐倉市の京成臼井駅前のショッピングセンター「レイクピアウスイ」のテナント店舗と、駅前商店街「臼井王子台商店会」からなる組織です。これまでに、レイクピアウスイ館内へのWi-Fi導入、インバウンド向け地域観光情報サイト「グローバルウスイ」の開設など、デジタル施策に力を入れてきました。
2021年度はデジタル施策だけにとどまらない新たな展開として、空き店舗スペースを活用したコミュニティスペースの新設を目指して研究会をスタートしました。

このスペースは単なる「市民の憩いの場」の機能だけでなく、多様な人材の交流拠点、地域ビジネスの活動拠点などに成長することを目的としています。また、リアルとバーチャル、オンラインとオフラインがつながるプラットフォームのような機能も持たせられれば、との希望と期待もあります。
スペースの新設にあたっては、千葉県中小企業団体中央会のサポートにより、経済産業省の事業再構築補助金を獲得。「うすいコミュニティひろば」の名称で2022年2月に正式オープンを迎えました。
誰のための場所?
研究会では、具体的な設計や費用など事務的な議論も必要でしたが、初期のコンセプトを決める段階では「誰のための場所にするか?」の議論にも時間を費やしました。
「マインドマップ」というフレームワークを使いつつ、参加者の自由な意見をまとめていくと「子育て世代向け」というキーワードが浮かんできました。ですが、研究会の参加者は講師である私も含め、全員が「男性・おじさん」。このメンバーだけで子育て世代を語るには多様性に欠けるということで、レイクピアウスイに入る保育園の職員さんにアンケートを実施するなどして意見を募りました。
運営方法などの調整で、まだ子育て世代向けのイベントは実施されていませんが、今後、さまざまな地域の関係者を巻き込みながら、子育て世代にも使ってもらえるようなイベントを展開していく予定です。

「うすいコミュニティひろば」のオープンにあたっては、告知用のホームページを新設するとともに、佐倉市民をターゲットにしたインターネット広告(スマホやPCなどで閲覧できるネット上の広告)も同時に配信し、デジタルを活用した認知向上を展開しています。
ネット広告を配信すると、世代や年齢ごとにどんなユーザーが広告に興味を持ったかがデータとして分かります。配信結果をみると、「女性・30代以上」の反応が良いことが分かり、当初コンセプトの「子育て世代向け」が実際のニーズと一定程度合致していたことが裏付けられました。
「子育て世代向け」のコンセプトは、最初は研究会メンバーの仮説に過ぎませんでしたが、ネット広告を配信してデジタルデータが得られたことで、仮説から「確かな進むべき方向性」へと進化しました。こうしたデジタルデータの使い方は「デジタルを手段として活用すること」の好事例といえます。
まとめ:デジタル化は「手段」
臼井地区商店会連合会がこれまで取り組んできたWi-Fi環境の整備やインバウンド向けサイトの開設は、ともすると研究会メンバーが「こうしたい」と思ったことを実現する取り組みでした。言い換えれば「デジタル化を進めること」が「目的」になっていたのです。
ですが、「うすいコミュニティひろば」の開設に伴うコンセプト決めやネット広告配信のフィードバックを通して、追い求めなければならないのは「誰に」「どうやって」「どんな風に」使ってもらうか、という利用者目線の運営だということが見えてきました。デジタルは「手段」という認識が少しずつ広がり、デジタルを活用した先にどんな利用者の体験が提供できるかを考えていく土壌ができてきたといえます。

このように臼井地区商店会連合会は、2021年度の研究会を通して「デジタル化の罠」から一歩抜けだし、デジタルをうまく活用しながら利用者の体験をどう提供していくか、という新たな次元での事業展開に取り組みつつあります。2022年度はショッピングモールの店内に開かれた「うすいコミュニティひろば」を会場に研究会を開催し、利用者目線での体験の実現を模索していきます。
本稿をお読みの組合の皆さんも、①デジタル化は「目的」ではなく「手段」である、②デジタル化の実現の先に利用者(顧客・消費者)の体験が向上することを目指すべきだ、という2点を押さえてデジタル施策に取り組まれることが望ましいと考えます。
(株式会社千葉日報デジタル 中島悠平)
※この記事は、千葉日報デジタルが2021年度に情報発信を全面的にサポートさせていただいた臼井地区商店会連合会様(千葉県佐倉市)の取り組みをまとめたものです。千葉日報デジタルと包括提携を結ぶ千葉県中小企業団体中央会様の会報誌「中小企業ちば」(令和4年4月号)に掲載の内容を転載しています。
市原商工会議所様主催で3月26日に市原市内で開かれた「いちはら未来創業フェスタ2022」に、千葉日報デジタルが運営サポート、インタビュアーなどの役割で運営参加させていただきました。

このイベントは、「SDGs」の考え方を地域の持続可能な発展につなげ、地域経済の将来を担う創業者にもそうした視点で創業に取り組んでもらえれば、との趣旨で企画されました。
当日はSDGsの専門家による講演、市原商工会議所・榊原会頭と千葉日報デジタルとの対談などが行われ、会場参加だけでなくYouTube配信でも多くの創業者・創業予定者が学びを深くしていました。
市原商工会議所様と千葉日報デジタルは2022年度、創業者支援、事業者支援でタッグを組み、デジタルマーケティングを学ぶ講座やプレゼン力を高めるワークショップを共同で開催していく予定です。
イベント当日の様子は、以下の「千葉日報オンライン」記事からご確認いただけます。
記事はこちら。 SDGsの推進に向け、千葉県が創設した「ちばSDGsパートナー登録制度」に千葉日報デジタルも登録を申請し、本日登録が完了しました。
199番目の登録となりました。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/sdgs/chibasdgs151-200.html
弊社の宣言書は以下の通りです。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/sdgs/documents/chiba199.pdf
地元メディアグループとして、SDGsの取り組みそのものを推進することも心がけつつ、メディアとして個々の取り組みの情報発信にも力を発揮できればと考えております。
 契約締結により、両社の既存顧客に対し、互いの商材・サービスの利用を紹介・仲介できるようになります。
契約締結により、両社の既存顧客に対し、互いの商材・サービスの利用を紹介・仲介できるようになります。アナログとデジタルの垣根を越えて「相互送客」を実現することで、互いに新規顧客の獲得につながる相乗効果を生み出すとともに、同じ千葉県を経営基盤とする企業として、互いの成長ひいては千葉県経済の活性化に寄与することを目指します。
詳しくは、以下のプレスリリースをご覧ください。
プレスリリースはこちら。
千葉日報社・千葉日報デジタルは7月21日、千葉県商工会連合会様と包括提携を結ばせていただきました。 提携により、連合会に所属する地域事業者の皆さまが、千葉日報グループの持つ情報発信のノウハウやネットワークを有効活用できるようになります。
提携により、連合会に所属する地域事業者の皆さまが、千葉日報グループの持つ情報発信のノウハウやネットワークを有効活用できるようになります。
デジタル化が進展する社会において、地域事業者の皆さまが自らデジタル媒体を絡めた新たな情報発信力を身につけることを目指すとともに、各事業者の事業成長ひいては千葉県経済の活性化につながることを目指していきます。